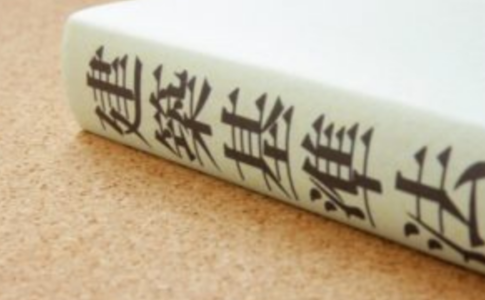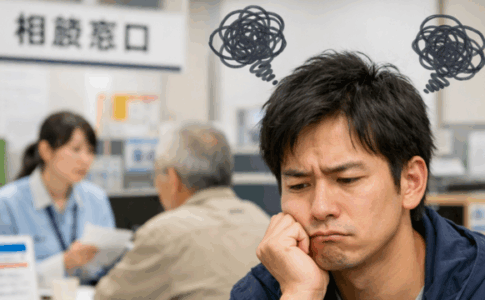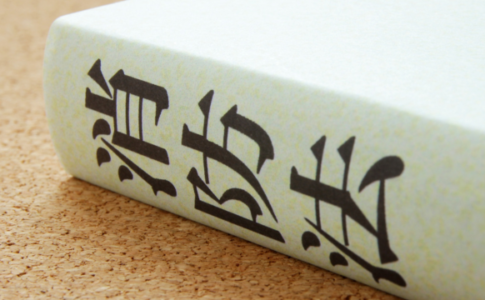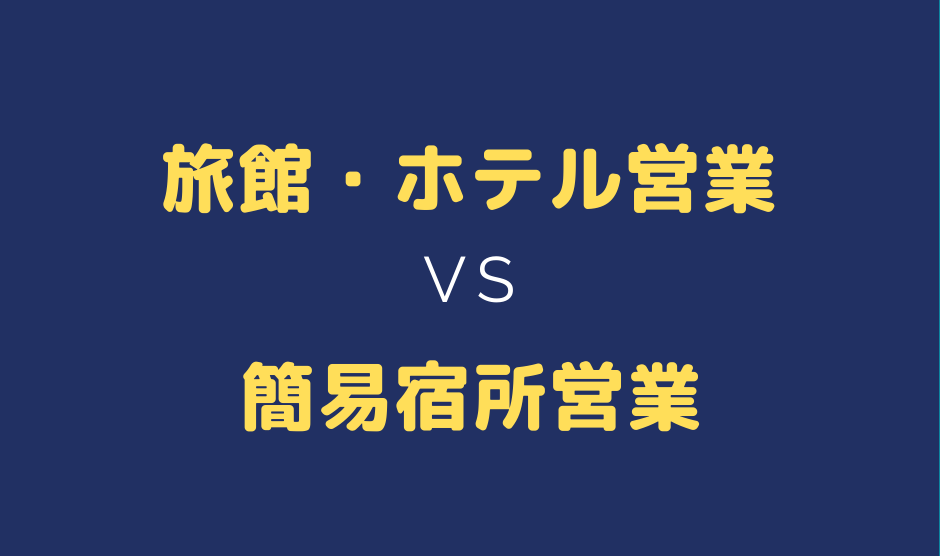はじめに
民泊を始めようと物件を探していると、「このエリアは用途地域が〇〇だから民泊できないかも」といった言葉に出くわすことがあります。
でも、民泊初心者にとって「用途地域って何?」「それがどう関係あるの?」という疑問は自然なものです。
結論から言えば、用途地域は「どんな建物や事業をしていいか」を決める街のルール。
このルールに合わない場所で民泊をやろうとすると、届出や許可が通らないことがあります。
たとえば、「第一種低層住居専用地域」は基本的に住宅のためのエリアで、商売をするには不向きな場所。
反対に「商業地域」などは店舗やホテルが建ち並ぶことを前提としており、民泊もスムーズに進むケースが多いです。
つまり、”用途地域を理解することは、物件選びの「最初の関門」”なんです。
この記事では、民泊と用途地域の関係をシンプルに整理していきます。
初心者でもすぐに理解できるように、専門用語をできるだけ噛み砕いて説明していきますので、安心して読み進めてください。
用途地域ってそもそも何?
「用途地域(ようとちいき)」とは、そのエリアにどんな建物を建ててよいか、何の目的で使ってよいかを決めるルールのことです。
これは都市計画法という法律で定められており、住宅街・商業地・工業地など、それぞれの地域にふさわしい建物や使い方を制限しています。
簡単に言えば、
- 住宅街に工場が建たないように
- 商業地に静かな住まいを求める人が困らないように
といった目的で整備されたルールです。
用途地域は全部で12種類!
用途地域は、以下の12種類に分かれています。
| 分類 | 用途地域名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅中心。商売は基本NG。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 住宅+小規模店舗などもOK。 | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中層住宅向け。静かな環境を維持。 | |
| 第二種中高層住居専用地域 | 住宅+病院や学校などもOK。 | |
| 第一種住居地域 | 住宅中心。小規模ホテルや店舗も可能。 | |
| 第二種住居地域 | 住宅+カラオケ店などもOK。柔軟性あり。 | |
| 準住居地域 | 幹線道路沿いなどに多い。車関連の店舗も可。 | |
| 商業系 | 近隣商業地域 | 住宅+店舗が混在。民泊に向いている。 |
| 商業地域 | ホテルやオフィスなど自由度が高い。 | |
| 工業系 | 準工業地域 | 工場+住宅の混在地。民泊も比較的やりやすい。 |
| 工業地域 | 住宅可だが制限あり。 | |
| 工業専用地域 | 住宅NG。民泊は不可。 |
これらの用途地域は、各自治体が公開している「用途地域マップ」や「都市計画図」で確認することができます。
民泊を始めるうえでは、「そのエリアがどの用途地域なのか」を最初にチェックしておくことが重要です。
なぜなら、同じように見える住宅街でも、用途地域が違えば、民泊の可否や条件がまったく変わってくるからです。
民泊ができる用途地域・できない用途地域
民泊を始めるときに見落としがちなのが、「その場所で本当に民泊ができるか?」というポイントです。
この可否は、「どの法律で運営するか」と「用途地域の種類」によって変わります。
ここでは、主な民泊の運営方法ごとに、使える用途地域・使えない用途地域を整理していきます。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の場合
民泊新法では、住宅として使用されている建物であれば、用途地域に関係なく届出が可能とされています。
ただし例外もあります:
- 自治体が「制限区域」「禁止区域」を条例で定めている場合、そのエリアでは届出できないことがあります。
- 実際には、第一種低層住居専用地域などでは土日祝日しか営業できない等、条件が厳しくなるケースが多いです。
そのため、用途地域がOKでも、自治体のルールや地域の実情を確認することが大切です。
旅館業の場合
旅館業で民泊を行う場合は、用途地域によっては許可そのものが下りないことがあります。
簡易宿所が許可される用途地域は、以下のとおりです。
| ✅許可可能 |
|---|
| 第一種住居地域 |
| 第二種住居地域 |
| 準住居地域 |
| 近隣商業地域 |
| 商業地域 |
| 準工業地域 |
一方、以下の地域では原則として旅館業の許可は下りません:
| ❌許可不可 |
|---|
| 第一種低層住居専用地域 |
| 第二種低層住居専用地域 |
| 第一種中高層住居専用地域 |
| 第二種中高層住居専用地域 |
| 工業地域 |
| 工業専用地域 |
このように、旅館業での民泊は住居専用地域では不可、商業系・住居系の一部でのみ可能と覚えておくとよいでしょう。
よくある誤解と注意点
- 「民泊はどこでもできる」は誤解!
→ 法律・制度・用途地域の組み合わせで可否が変わります。 - 「戸建てなら簡単」は危険な思い込み
→ 建物の形ではなく、用途地域と法律の方が重要です。 - 用途地域がOKでも、建物の用途変更・消防対応など別の壁がある
→ 次の章で詳しく説明します。
用途地域だけじゃない!民泊ルールの他のポイント
用途地域は民泊物件選びの第一関門ですが、それをクリアしただけで「すぐに運営できる」というわけではありません。
ここでは、用途地域以外に注意すべきポイントを2つに絞って紹介します。
① 建築基準法の制限
民泊を始めるには、建物が建築基準法で適法であることが前提です。
主に注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 接道要件:旅館業では「幅員4m以上の道路」に2m以上接していることが必要
- 採光・換気:窓の面積が基準に満たないとNG
特に、雑居ビルの1室などでの民泊は、基準を満たさず許可が下りないことがあるため、事前の確認が重要です。
参考:https://ryokangyoukyoka.com/archives/3824
② 消防法の対応
民泊では、宿泊施設としての消防設備が必須になります。
物件の構造や規模によって、必要な対策は大きく異なります。
主なチェック項目は以下の通りです。
- 自動火災報知設備の設置要件
- 誘導灯の設置が必要か
特に、共同住宅やビルの一室を使う場合は建物全体に自動火災報知設備が必要になるケースもあり、消防署との事前相談が欠かせません。
参考:https://ryokangyoukyoka.com/archives/6763
これだけ覚えればOK!用途地域チェックの3ステップ
「この物件、民泊に使えるかな?」と考えたときに、最初にやるべきなのが用途地域のチェックです。
とはいえ、すべての法律や資料を読み込む必要はありません。最低限、次の3ステップを押さえておけばOKです。
ステップ①:都市計画図や用途地域マップを確認
各自治体のホームページでは、「用途地域マップ」や「都市計画図」が公開されています。
ここで物件の住所を入力すれば、その場所がどの用途地域に指定されているかを確認できます。
🔍 検索キーワード例:「◯◯市 用途地域 マップ」
💡 Googleマップでは用途地域は出てこないので注意!
ステップ②:該当用途地域が民泊に適しているかを照らし合わせる
地図で確認した用途地域が
- 民泊新法なら 原則OK(ただし自治体制限に注意)
- 旅館業なら OKな地域かNGな地域か をしっかり確認
ここまでで「そもそも民泊が可能かどうか」の大まかな判断ができます。
ステップ③:自治体に直接確認する
地図や一覧表で判断できても、最終判断は各自治体の運用によります。
とくに旅館業許可や条例による制限が関わる場合は、必ず保健所や建築課などの担当窓口に問い合わせるのがおすすめです。
問い合わせ時は、
- 住所
- 用途地域
- 民泊の予定の運営方法(民泊新法 or 旅館業)
この3点を伝えるとスムーズに対応してもらえます。
この3ステップを押さえておくだけで、無駄な物件選びやトラブルをぐっと減らせます。
まとめ
「民泊=むずかしそう」「法律が複雑で不安」という声は、初心者の方からよく聞かれます。
でも実際には、押さえるべきポイントは限られています。
この記事では特に重要なポイントとして、以下の内容を整理しました:
- 用途地域には12種類あり、民泊ができる場所とできない場所がある
- 民泊新法は比較的柔軟だが、旅館業は用途地域の制限を強く受ける
- 用途地域だけでなく、建築基準法や消防法、保健所の基準も重要
- 用途地域の確認は、マップで調べて→表で照らし→自治体に確認するのが鉄則
民泊は、きちんとルールを理解して準備すれば、初心者でも十分に始められるビジネスです。
最初は難しく感じるかもしれませんが、この記事のようにひとつひとつ整理していけば、自然と知識も身につきます。
物件探しや準備を進める中で不安になったときは、専門家のサポートを活用するのも一つの手です。
自分に合った進め方で、一歩ずつ理想の民泊運営を実現していきましょう!
この記事のQ&A
Q1. 用途地域って何ですか? 民泊とどう関係があるんですか?
用途地域とは、「その場所で何をしていいか」を定めた都市計画上のルールです。
民泊を始めるには、法律や自治体ルールとともに、この用途地域が「民泊に適しているかどうか」を確認する必要があります。
Q2. どの用途地域なら民泊ができますか?
- 民泊新法:原則すべての用途地域で可能。ただし自治体によって制限されている場合があります。
- 旅館業(簡易宿所):第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域でのみ原則許可されます。住居専用地域や工業系地域では基本NGです。
Q3. 「戸建てなら民泊しやすい」って本当?
戸建て=民泊OKではありません。用途地域や建物の構造、自治体ルールなど複数の条件が整って初めて運営できます。
Q4. 用途地域だけ確認すれば民泊できますか?
いいえ。用途地域はあくまで第一段階です。
他にも、建築基準法(接道要件・採光・換気など)や消防法(自動火災報知設備・誘導灯など)への対応が必要です。
Q5. 用途地域はどうやって調べればいいですか?
各自治体のホームページで「用途地域マップ」や「都市計画図」が公開されています。住所を入力すれば用途地域が確認できます。
Q6. 用途地域を確認したら、あとはどうすればいい?
以下の3ステップで進めるのが基本です:
- 用途地域マップで確認
- 民泊の制度ごとの適否を照らし合わせる
- 最終的に自治体(保健所・建築課など)へ確認する
Q7. 消防法はどこまで対応が必要ですか?
建物の構造や規模によって異なりますが、特に共同住宅やビルの一室では、建物全体に消防設備が必要になる場合もあるため、事前に消防署へ相談することが大切です。
Q8. 初心者が一番最初に確認すべきポイントは?
「用途地域」と「自治体の民泊に関する条例」です。これを見誤ると、契約した後に民泊できないことが発覚するリスクもあるので、最初に必ずチェックしましょう。