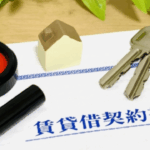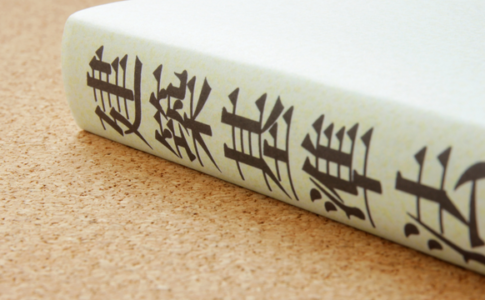はじめに
「民泊、副業として興味はあるけれど、正直どこから手をつけていいかわからない…」
そう感じている会社員の方は、実は少なくありません。特に本業が忙しく、時間も限られている中で、物件選び・法制度・収支のシミュレーションなど、多くの要素を一人で調べて進めるのは至難の業です。
この記事では、忙しい会社員でもスムーズに一歩を踏み出せる「失敗しない物件選びの3ステップ」を、民泊運営のプロの視点からわかりやすく解説します。
情報に振り回されず、自分のペースで副業としての民泊を始めたい方へ。
この記事があなたの「最初の一軒」を後押しできれば幸いです。
【ステップ1】制度を理解して「できる場所」を把握する

民泊を始めるには、まず「どこで、どんな制度なら営業できるのか」を理解することが第一歩です。
ここを曖昧にしたまま物件を決めてしまうと、「借りたのに営業できない…」という大きなリスクにつながります。
民泊には2つの制度がある
副業民泊で主に選ばれるのは、以下の2つの制度です。
| 制度名 | 特徴 | 営業日数制限 |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 届出だけで始められる簡易な制度 | 年間180日まで |
| 旅館業 | 営業日数の制限なし。許可申請が必要 | 制限なし |
「180日まででもOK」「まずは小さく始めたい」という人は【住宅宿泊事業】、
「しっかり収益を出したい」「年間通して稼働させたい」という人は【旅館業】を選ぶことが多いです。
制度ごとに「できる場所」が違う
民泊はどこでもできるわけではありません。
法律で定められた「用途地域」や自治体の「上乗せ規制」によって、営業できる場所・できない場所が決まっています。
- 【住宅宿泊事業】は、ほとんどの用途地域で基本OK
- 【旅館業】は、商業地域・近隣商業地域など“旅館・ホテル”が許される場所でしかNG
さらに自治体によっては、
- 平日NG/週末のみOK
- 日数制限あり
などの独自ルール(上乗せ規制)もあるため注意が必要です。
参考記事:【2025年版】民泊初心者でも使える!用途地域と民泊ルールの超シンプル整理
【ステップ2】物件の条件を整理して「できる物件」を見極める

制度とエリアのルールを理解したら、次は「あなたの民泊が可能な物件かどうか」を見極めるステップです。
民泊は普通の賃貸とは違い、条件がいくつもあります。
特に注意すべきポイントは次の4つです。
① 用途地域と制度のマッチ
すでに確認したように、「用途地域」によって選べる制度が異なります。
- 住宅宿泊事業:第一種低層住居専用地域などでも可で幅広くOK
- 旅館業:商業地域など限られた地域のみ
物件がどの用途地域にあるかは、市区町村の都市計画図やネットで確認できます。
| 旅館業許可OK | 旅館業許可NG |
|
|
② 消防法上の制約
民泊は消防法では「旅館等」として扱われます。
そのため、建物の構造や規模によっては自動火災報知設備(特小自火報など)の設置が必要になることがあります。
- 延床面積が300㎡以下 → 比較的緩和あり
- 3階建て以上の戸建て住宅/階段が1つしかないマンション・アパート → 対策コストが大きくなる可能性あり
事前に所轄の消防署に相談することが重要です。
参考記事:【保存版】民泊を始めるなら知っておくべき消防法の基本と対策
③ 建築基準法のチェック
旅館業で営業する場合、「居宅」から「旅館・ホテル」への用途変更が必要です。
ただし、使う面積が200㎡以下なら建築確認申請が不要になる特例があります。
参考記事:【2025年最新版】民泊を始める時に見落としがちな建築基準法について徹底解説
④ 管理規約の有無(マンションの場合)
マンションの場合は、管理規約で民泊禁止されていないかが最大の壁。
禁止されていると届出も許可も出せません。
内見時や契約前に、必ず管理規約を確認しましょう。
参考記事:マンションの空き部屋で民泊を始めるための7つのステップ
このように、民泊が「制度的にできる場所」でも、物件の条件によっては営業が難しいことがあります。
そのため、制度 × エリア × 物件条件の三重チェックが成功のカギになります。
【ステップ3】準備・届け出に向けて動き出す
物件の条件もクリアできそうであれば、いよいよ民泊営業に向けて「動き出す」フェーズです。
とはいえ、会社員として忙しく働いていると、どこから手をつけていいか分からないことも多いですよね。
このステップでは、民泊スタートに向けた具体的な準備と手続きを3つの観点で紹介します。
① 事前相談(保健所・消防署)
民泊は行政への「届出」や「許可申請」が必要です。
その際にスムーズに進めるためには、事前に保健所や消防署に相談しておくことが非常に重要です。
- 住宅宿泊事業(民泊新法):保健所への「届出」が必要
- 旅館業:保健所への「許可申請」が必要
消防署にも、感知器の設置範囲や設備条件について相談します。
自治体ごとに解釈が異なることもあるので、「とりあえず相談」が一番の近道です。
② 必要書類と契約の準備
相談と並行して、必要な書類や契約関係も準備しておきましょう。
- 建物所有者の使用承諾書(賃貸なら大家さんから)
- 図面(平面図・配置図など)
- 住民票・身分証など
- 住宅宿泊管理業者との契約書(新法の場合)
また、清掃・ゴミ出し・ネット環境・緊急対応など、実際の運営面の体制も固めていきます。
「後でやろう」と思うと時間が足りなくなるので、早めに並行で動くのがおすすめです。
③ タイムラインを決めて逆算する
本業が忙しい方こそ、スケジュール感を持つことが成功のカギになります。
たとえば:
- 今月中に消防と保健所の相談
- 来月に契約&設備手配
- 再来月に営業開始
というように、逆算してタスクを分解すると迷いなく動けます。
「進めてOKな物件」かどうかが早くわかれば、その分だけスピード感を持って準備ができます。
参考記事:【空家賃を最小化】賃貸民泊の効率的な立ち上げロードマップ
「わかっていればもっと早く動けたのに」をなくすために
物件の制度的な可否や、必要な設備条件が最初から分かっていれば、
余計な迷いや調査の時間を減らすことができます。
民泊物件GPTでは、物件の住所や構造を入力するだけで「できる/できない」「必要な確認項目」が一目で分かる仕組みです。
忙しい方こそ、こうしたツールを活用して時間を節約しながら、着実に前に進んでください。
まとめ:最初の一歩は「物件選びの正しい判断」から
副業として民泊を始めたい会社員にとって、一番のハードルは「この物件で本当にできるのか」という不安です。
闇雲に進めてしまうと、契約後に「制度的に不可だった」「消防対策に莫大なコストがかかった」といった失敗につながりかねません。
だからこそ大切なのは、以下の3ステップです。
- 制度を理解し、営業できるエリアを把握する
- 物件の条件(構造・面積・規制)を整理して見極める
- 行政相談や書類準備を進め、計画的に動き出す
この流れを押さえれば、忙しい会社員でも迷わず民泊の準備を進めることができます。
「もっと早く進めればよかった」と後悔しないために、まずは候補物件の可能性を正しく把握することが第一歩です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事のQ&A
Q1. 民泊制度はどこで調べればいいですか?
A1. 市区町村の都市計画図やホームページで用途地域を確認し、届出が必要な「住宅宿泊事業(民泊新法)」や許可が必要な「旅館業」のどちらにするか判断してください。自治体独自の規制(営業日数や住民同意など)がある場合もあるため、必ず確認しましょう。
Q2. 消防署には具体的に何を聞けばいいですか?
A2. 具体的な建物の情報を伝え、「自動火災報知設備(特小自火報など)」や避難経路の要件についてご相談ください。
Q3. 建築確認申請が不要になる条件とは?
A3. 旅館業を始める場合でも、民泊として使う面積が200㎡以下なら、建築用途の変更や建築確認申請が不要になる特例があります。ただし自治体によって判断が異なることもあるため、事前相談が推奨されます。
Q4. マンションで民泊する場合の注意点は何ですか?
A4. 最大の壁は管理規約。他の住人が「民泊禁止」と定めていると、届出や許可ができないことがあります。契約前に必ず管理組合や管理規約を確認してください。
Q5. 働きながらでも民泊の準備は可能ですか?
A5. はい、「ステップ1〜3」に沿って、制度理解→物件チェック→行政相談や書類準備までをスケジュール化すれば、忙しい会社員の方でも十分に進められます。特に「逆算型タスク管理」が成功の鍵です。
Q6. 「民泊物件GPT」ってどう活用するの?
A6. 物件の所在地・構造・面積などを入力すれば、制度的な可否や必要な手続き・注意点が整理されて返ってくるAIツールです。忙しい方でも短時間で判断材料を整理できるため、最初の一歩に役立ちます。